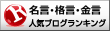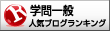運動
発達障がいのなかには、体の動かし方がぎこちなかったり
手足の協調運動が苦手な子どもがいます。
不得意な部分をカバーする運動
を練習する事で次第に動きがスムーズになっていきます。
ケースの具体例
- ボールを使った運動が苦手
- 縄跳び、跳び箱がうまく跳べない
- 音楽や指示に従って動けない
- 走るのが苦手
- 片足立ちができない など
上記のようなケースがあります。
他にもボールの追視や動きを真似て動く
止まったり動いたりという動作が難しい場合があります。
- 疲れやすい
- 座り込んでしまう
- 姿勢保持が難しい
が困難な子供もいます。
なぜそのようになるのか?
運動が苦手な理由
- ボディイメージが弱い
- 緊張、緩和のコントロールが苦手
- 人の動きを見て真似るのが苦手
上記が苦手な子ども達は
脳の情報ネットワークに未発達な部分があり連絡がうまくいかないことで起こります。
それにより
指先や腕、脚の力が入らなかったり、逆に力を抜く事が上手くできない場合があります。
対処法
到達目標を下げてあげる事が重要。
これは
スモールステップ
と呼ばれています。
- できそうなことからやらせる
- 成功体験をつませてあげる
- 一つ一つ褒めてあげる
要求や期待が高いとプレッシャーになってしまいます。最悪投げ出してしまう。
まずは興味を引かせ
成功する喜びを与えてあげる
ご褒美シールなど目に見えてわかるものがあればあると良いかもしれません。
ここで重要なのは
- 自信をつけさせてあげる
- 劣等感をもたせない
- 集団で運動を行う場合まわりの子達への配慮
が必要です。
できなくて恥ずかしい。と最初からあきらめてしまうケースが多いのです。
最初からできる人なんていない。絶対できるよ。大丈夫!!
と声をかけてあげてください。
間違っても
なぜできないんだ。
こんな簡単な事できるだろう。
やる気ないのか。
と否定的な言葉はダメです。
さらに抽象的な
「ちゃんと」とか「集中」とか
言葉掛けもNGです。
療育といわれる現場では
肯定的な言葉掛け
が必要になってきます。
練習方法
- だるまさんがころんだ
- 旗揚げゲーム
- 障害物を使った運動
など感覚を養える運動が良いと思います。
練習というイメージというよりは
遊び
という感覚を持たせてあげるといいかもしれません。
飲食業で言われる1way2jobじゃないですが
楽しんで複数の感覚を養えるという効果があります。
いずれの練習も
本人ができそうな目標を設定し
できたー!という達成感を味わせてあげる事が大切です。
家庭での配慮
家庭でも練習させてあげたい時
重要な事があります。
- 特訓にならない
- 勝負にこだわらない
- 楽しみながら
- 指導者と言ってる事が違わないようにする
我が子ができるようになってくると…期待が高まってしまいますよね。その分熱も入り心に余裕がなくなってきてしまいます。
特に子どもの場合敏感で
ママになにがわかるの!
パパには出来ないくせに!
など反発してしまいます。
それじゃ全く意味がない。
引っ張ろうとすると引っ張られるのです。反作用です。
なので同じ目線に立って同じ目標に目を向けて
一歩ずつ進んでいく事が重要です。
親のエゴだけでは子供は成長しません。
各ご家庭で楽しんで運動に取り組んでみて下さい♪♪
またご相談がある場合は各SNSで受け付けておりますのでDM下さい☺︎